蓄電池導入でどのくらい節約できる?電気代が高い家庭におすすめ!

はじめに
「最近、電気代が高くなったなぁ」と感じている方は多いのではないでしょうか。特に2022年以降は、燃料費の高騰や再エネ賦課金の上昇などにより、家庭の電気料金は右肩上がりです。そんな中で注目されているのが 「家庭用蓄電池」 です。実際に、蓄電池をつけると電気代はどのように変化するのでしょうか?この記事では、電気代がどのように節約できるのか、仕組みから導入効果、具体的なシミュレーションまで分かりやすくご紹介します。
もくじ
蓄電池ってどんなもの?

蓄電池は簡単にいうと「電気をためて、必要なときに使える大きな充電池」です。スマホやノートパソコンのバッテリーと仕組みは同じで、ただ容量が家庭用に合わせて大きくなっています。主な利用シーンは以下の通りです。
-
電気代の安い時間に充電して、高い時間に使う(時間帯別料金対策)
-
太陽光発電で余った電気をためて、夜に使う(自家消費率アップ)
-
停電時に電気を確保(非常用電源)
中でも、電気代に直結するのが 時間帯による使い分け と 太陽光との組み合わせ です。
蓄電池が電気代を安くする仕組み

では、なぜ蓄電池を導入すると電気代が下がるのでしょうか?
・ 電気代の「時間差」を活用
多くの電力会社では、夜間の電気料金が安く、昼間は高く設定されています。たとえば「昼は1kWhあたり30円、夜は15円」といった具合です。蓄電池があれば、夜間の安い電気をためておき、昼間の高い時間帯に使うことが可能です。つまり、同じ電気を使っても半分のコストで済む ということ。
・太陽光発電とのセットでさらに効果大
太陽光パネルを設置している家庭では、昼間に発電した電気をそのまま使うのが一番お得です。しかし、発電量が余ると売電に回ります。以前は売電単価が高く(40円/kWh前後)、売る方が得でしたが、現在は15円まで下がっています。一方で、買う電気の料金は30円を超えていることも多いので、余った電気を売るより 自分でためて夜に使う方が経済的 なのです。
・ ピークカットで基本料金を抑える
一部の電力会社では、同時に使う電力量(ピーク電力)が契約容量を決め、基本料金に反映されます。蓄電池があれば、電力の使用が集中する時間帯をカバーでき、契約容量を抑えて固定費を減らす効果もあります。
蓄電池を導入した場合のシミュレーション
ここで、実際にどのくらい電気代が下がるのかをイメージしてみましょう。
モデル家庭
-
4人家族
-
月の電気使用量:400kWh
-
電気代:およそ12,000円/月
-
太陽光発電:5kW設置済み
-
蓄電池:容量9.8kWhタイプ
蓄電池なしの場合
-
昼間:太陽光で賄いきれない分は買電(30円/kWh)
-
夜間:買電(30円/kWh)
-
余剰電力は売電(15円/kWh)
→ 電気代約12,000円 − 売電収入約3,000円 = 実質9,000円前後
蓄電池ありの場合
-
昼間:太陽光でまかない、余った分は蓄電池に充電
-
夜間:買電せず蓄電池から放電
-
売電は少なくなるが、自家消費率は大幅に向上
→ 電気代約12,000円 − 売電収入1,000円 +買電削減効果約5,000円 = 実質6,000円前後
毎月3,000円前後の節約効果 が期待でき、年間にすると約36,000円の削減になります。
※各家庭合った蓄電池選びもポイントです!蓄電池選びはこちらをチェックしてみてください。
蓄電池導入のメリットと注意点
メリット
-
電気代が安くなる
-
停電時でも安心
-
太陽光の自家消費率が上がり「電気を買わない生活」に近づく
-
将来の電気代高騰リスクを軽減できる
注意点
-
初期費用がかかる
-
家庭の電気使用量や生活スタイルによって効果が変わる
蓄電池は「投資」か「安心」か
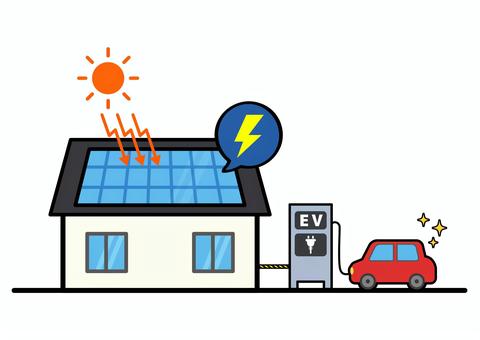
蓄電池を導入する理由は、大きく分けて2つです。
-
経済性を重視する投資的な考え方
電気代の削減や、売電価格低下への対策として導入するケース。 -
安心を重視する生活防衛的な考え方
台風・地震など災害時の備えとして「停電でも電気が使える安心感」を買うケース。
実際はこの両方を兼ね備えているのが蓄電池の魅力です。
補助金制度を活用しよう
国や自治体では、再エネ推進の一環として蓄電池の導入補助金を設けている場合があります。たとえば、
-
国の「DR補助金」※2025年度は終了しております。
を利用すれば、数十万円の助成を受けられることも。導入コストを下げれば、経済効果はさらに高まります。
まとめ
蓄電池を導入すると、
-
安い電気をためて高い時間に使える
-
太陽光発電の自家消費率が上がる
-
停電対策にもなる
という効果で、電気代を大きく抑えることが可能です。初期投資は必要ですが、毎月の電気代が下がり、将来的な電気代高騰リスクも回避できます。さらに補助金制度を利用すれば、よりお得に導入できるチャンスもあります。「電気代を少しでも減らしたい」「将来の安心も手に入れたい」――そんな方にとって、蓄電池はこれからの暮らしを支える心強い味方になるでしょう。



